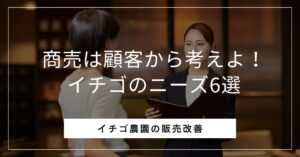農業コンサルタントに興味があるけど、デメリットが気になりませんか?
- 農業コンサルタントって詐欺師じゃないの?
- 農業コンサルタントって役に立たないんじゃないの?
- 農業コンサルタントなんてお金の無駄じゃないの?
と思ってる方はぜひ最後までお読みください。
この記事では農業コンサルタントのデメリットを10個紹介します。
この記事を読めば、農業コンサルタントのデメリットを理解でき、ミスマッチを防げます。
1.現場を知らずに机上の空論ばかり言う
農業コンサルタントの中には、農業の生産現場のことを理解していない人がいます。
例えば、農業とは関係ない生活をしてきた、農作物の栽培をしたことがない人です。
これは、「農業分野の研究者」や「大学の教授」、「ネットの情報でわかった気になる素人」なども同じ様な指摘を受けることが多いです。
「◯◯という画期的な農法があるから、それを取り入れれば大成功する!」と主張しますが、その◯◯をこの土地ではできない理由や、その農園が取り入れない理由を理解していません。
この間違いを犯す原因は、実際の農業経営のことを理解していないからです。
2.成功事例を一般化しすぎて各農家の事情を無視する
農業分野にも、成功事例があります。
新聞やテレビ、ネットニュース、業界紙などで成功事例が取り上げられています。
その成功事例には、その農園ならではの「隠された成功要因」があります。
しかし、その隠された成功要因はメディアには取り上げられず、気がつく人が少ないです。
農業コンサルタントの中には、その隠された成功要因に気がつかず、他の農園にお勧めする人がいます。
なぜかというと、成功事例をパクって他の農園に教えるのが「楽だから」です。
テンプレート化した施策を、複数の農園に横展開している会社もあります。
しかし、隠された成功要因に気がつかないので、成功要因をマネしても成功しません。
これは「農業以外の分野の経営コンサルタント」も多く犯すミスです。
3.高額なコンサル料に対して効果が不透明
農業コンサルタントの料金は高額な場合が多いです。
例えば、農業普及員は公務員なので仕事をお願いしても、無料で対応してくれます。
JAの営農指導員もJAの部会員でJAに農作物を出荷していれば、無料で対応してくれます。
しかし、農業コンサルタントに仕事を依頼すると、「有料」です。
お金を払わないと業務を行ってもらえません。
理由は農業コンサルティング企業が「民間企業だから」です。
ただし、これは農業以外の分野の「戦略コンサルタント」や「経営コンサルタント」も同じです。
無料で業務を行うコンサルタントは、コンサルタントではなく、ボランティアです。
コンサルティングの成果
コンサルティングの効果については、業務内容や課題、売上規模などで変動します。
コンサルタントに依頼できる業務内容は栽培から販売、経営、組織化などさまざまあります。
依頼する農園の売上規模も、開業前で0万円程度、1,000万円程度、1億円程度、10億円程度など、さまざまです。
具体的な業務内容や売上規模などがわかれば、効果の予測は立てられます。
ただし、コンサルタントに仕事を依頼した経験がない人の場合、効果の予測ができません。
特に農園はコンサルタントに依頼した経験がない人が多いです。
農業以外の業界では、コンサルタントに依頼するのは当たり前になっています。
4.実務経験が浅いのに専門家を名乗る
農業コンサルタントの中には、実務経験が浅い人がいます。
例えば、以下のような人です。
- 自分で農作物を栽培した経験がないが、栽培コンサルタントを名乗る人
- 自分で会社経営をした経験がないが、経営コンサルタントを名乗る人
- 自分で病害虫防除をした経験がないが、病害虫防除コンサルタントを名乗る人
- 自分で販売をした経験がないが、農作物販売コンサルタントを名乗る人
- 自分で補助金を活用した経験がないが、補助金コンサルタントを名乗る人
なぜ、実務経験が浅いのに専門家を名乗るのでしょうか?
それは、農業コンサルティング企業が新卒や中途人材を採用し、できるだけ早くコンサルタントとして業務を任せたいからです。
新卒や中途人材を教育し実務経験を積ませたいと思ったら、本当は5〜10年程度は経験を積ませたいです。
ですが、5〜10年もの長い時間をかけて教育をする余裕はありません(人件費で赤字になるから)。
そのため、採用から0〜1年程度のOJT教育を経て、経験が浅い状態でコンサルタントとして業務を任せます。
その結果、期待した専門性がない、未熟なコンサルタントが担当になり、成果が出ないことがあります。
5.実際の農作業やリスクを取らず責任を農家に押し付ける
農業コンサルタントの多くは、栽培失敗や売上減少のリスクを取りません。
ただし、これは契約内容によって変わります。
例えば、「成功報酬型」の契約であれば、栽培失敗や売上減少の責任をコンサルタントが取ります。
その代わり、栽培が成功したり、売上が改善した場合は、コンサルタントの取り分が大きくなり、農園の利益が小さくなります。
また、成功報酬型の場合は、業務遂行についてコンサルタントが意思決定をしたり、指示を出す必要があります。
そのため、コンサルタントが農園の「社長や副社長」などの重要な役職につき、人事や組織、栽培方法、販売方法などに口出しをすることになります。
コンサルティングについては、どのような契約内容なのか、契約前に確認するようにしましょう。
6.補助金の活用を勧めるだけで本質的な経営改善にならない
農業コンサルタントの中には、「補助金の取得」を専門にする人がいます。
農園経営を改善する手法として、補助金に頼っている場合です。
農業では活用できる補助金がありますが、補助金を活用しても農業経営がうまくいくとは限りません。
補助金を活用するために、割高なオーバースペックな設備を導入する必要が出ることが多いです。
「1億円の設備を補助金を使って5千万円で買えた!」と農業コンサルタントや農業経営者が自慢することがあります。
しかし、実際には適正な設備を選べば補助金なしでも5千万円で買えることあります。
また、「補助金が取れるから◯◯をやろう!」と補助金を取るために事業を始めるという、本末転倒なケースも多いです。
そのような事業は99%失敗に終わります。
補助金はあくまでも、農業事業のサポートです。
7.データやIT導入などのスマート農業を推奨するが農家の負担や現場を考えていない
農業コンサルタントの中には、とにかくデータ化やIT導入などのスマート農業を推奨する人がいます。
しかし、経営のことを考えると、ドローンやロボットなどの新しい設備等は資金繰りを悪化させます。
また、AIを使ったデータ分析などの新しい技術を使うと、それを従業員にマスターさせる教育コストもかかります。
農作業の多くは、手袋を着用したり、手が汚れていたり、両手が塞がった状態で行います。
農作業しながら、スマホやタブレット、パソコンの操作をするのは困難です。
オフィスでデスクワークをしている一般的な企業とは、農園は労働環境が違います。
また、農園経営者の中には、「あと5〜10年で農園を畳もう」と考えている人もいます。
その場合、スマート農業やIT導入は必要ないケースが多いです。
8.コンサルの成功例の紹介ばかりで失敗例や契約終了後の状態を公開
農業コンサルタントの多くは、コンサルの成功事例は紹介しますが、失敗事例や契約終了後の状態を公開しません。
100%の契約先が成功することはないので、失敗事例もあるはずです。
また、コンサルティングの契約期間が終わった後、その農園がどうなったのかも重要です。
契約期間はうまくいくけど、契約期間が終わったらうまくいかなくなったら意味がないからです。
失敗事例を公開しない理由は、契約内容が関わっています。
多くのコンサルティング契約では、「守秘義務の契約」が含まれています。
そのため、取引先のマイナスになるような失敗事例については、公開できない場合が多いです。
契約後の状態についても、守秘義務契約が継続していたり、勝手に取引先の経営状態を公開することはできません。
例えば、弁護士や依頼人の個人情報を公開したら大問題ですよね!?
コンサルタントも依頼人の情報を勝手に公開できません。
9.農家の信頼関係や地域コミュニティを軽視し経営効率だけを重視する
農業コンサルタントの中には、ビジネスの効率化だけを考えてしまう人がいます。
しかし、農業の世界は、一見非効率に見える作業が、実は重要であることが多いです。
それは、農業は周辺の農地や水利、コミュニティなどが関係するからです。
例えば、農業者の多くは、水路の清掃や土手の雑草刈り、地域のお祭り、消防団などに参加します。
これらは一見、農業経営には必要ない非効率で無駄な作業です。
しかし、このような行事や作業に参加しないと地域から孤立し、ひいては農業経営にも悪影響を与えます。
農業コンサルタントは、田舎や農村独特のムラ文化を理解していない人が多いです。
多くの農業コンサルタントが、農村で生まれ育っておらず、ムラ文化を知らないからです。
10.コンサルタント自身が農業経営で成果を出した実績が乏しい
農業コンサルタントの多くは、自分で農業経営で成果を出していません。
そもそも、農業コンサルタントとは、「農業経営者の上位互換」ではありません。
これは農業以外の分野でも同じで、コンサルタントは経営者の上位互換ではありません。
コンサルティングは、何かの分野について経営者の役に立つ職業です。
コンサルティングについて理解していない人は、ここを勘違いしています。
例えば、「日本最大級の農園を経営する農業経営者が農業コンサルタントを始めた」という話を聞かないですよね?
その理由は3つあります。
自社の農業経営に集中した方が良い
まず、農業経営がうまくいっている場合、その経営者はその農園の経営に集中します。
なぜかというと、それが一番効率的にお金を稼ぐ方法であり、社会貢献性も高いからです。
自分の農園の経営規模を拡大することを選択します。
もし、農園経営者が農業コンサルタント業を始めたとしたら、おそらく農園経営がうまくいっていないからです。
農園経営がうまくいっていれば、そちらに集中した方が良いからです。
ノウハウを他の農園に教えない
2個目は、農業経営がうまくいっている場合、そのノウハウを競合である他の農園に教えません。
もし他の農園にそのノウハウを教えてしまったら、自分の農園にマイナスな影響が現れます。
「企業秘密」や「成功の秘訣」は教えませんよね!?
もし教えていたとしたら、それは陳腐化した技術や役立つノウハウではありません。
コンサルタントに必要なスキル
3個目は、コンサルタントとしての業務が得意ではないからです。
優れた農業経営者が得意なことは、「自社の農業経営」です。
コンサルタントに求められるスキルは、「知識がない人にわかりやすく教えること」や「農業経営者に不足する何かの専門性」です。
農業コンサルタントは、「自社の農業経営」という分野では農業経営者よりも劣ったスキルですが、それ以外の何かの専門性を持ち、それをわかりやすく教えることを得意としています。
まとめ
今回は農業コンサルタントのデメリットを10個紹介しました。
農業コンサルタントは、使い方によって、良くも悪くも影響します。
例えるなら、料理人とフライパンの関係に似ています。
料理人が農業経営者で、フライパンが農業コンサルタントです。
料理人としてフライパンを上手に使いこなしましょう。
こんなお悩みはありませんか?
イチゴビジネスに新規参入したいけど…
◆イチゴ農園を始めたいけど、どうすればいいかわからない…
◆イチゴ農園の事業戦略や事業計画づくりに不安がある…
◆イチゴ農園の設備投資の金額を低く抑えたい…
>>イチゴ農園の新規参入で失敗したくない方はこちらをご覧ください。
イチゴ農園の栽培や経営を改善したい
●イチゴが花を咲かせなくて、収量が下がった…
●イチゴの病気や害虫を抑えられなくて、収量が減った…
●農園の経営が苦しいけど、どうしたらいいかわからない…
>>経営中のイチゴ農園を立て直したい方はこちらをご覧ください。